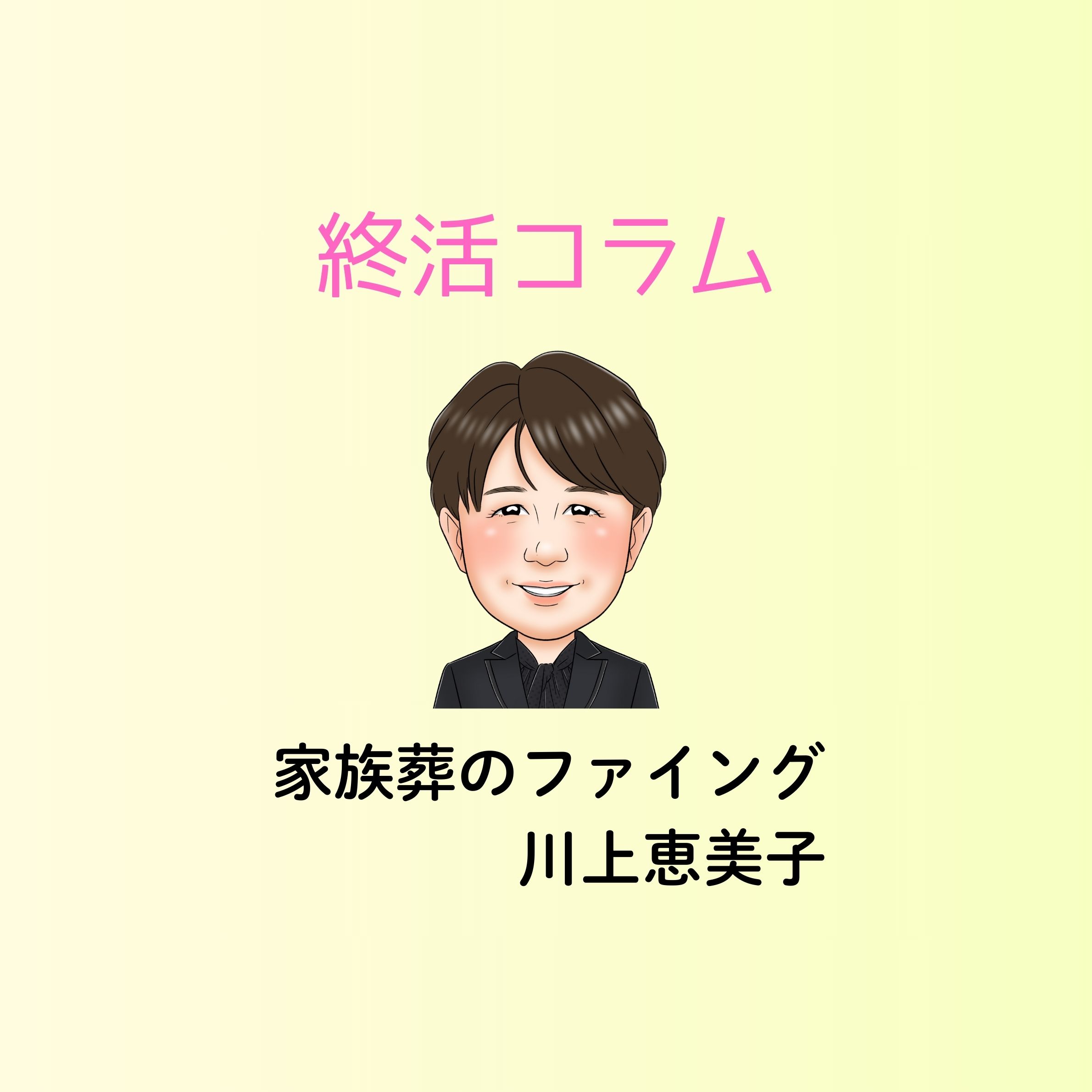
岡山市で葬儀・家族葬をお考えの方へ 岡山の直葬・葬儀・家族葬・一日葬なら家族葬のファイング【公式】[9.8万円~] 家族とはじめる終活終活カウンセラー 川上 恵美子 みなさん、こんにちは。家族葬のファイング、終活カウンセラーの川上恵美子です。 ~お葬式で必要な知識とは~ 「お骨の供養はどうお考えですか?」これは、私が岡山で葬儀のご相談を受けたときに、まず最初にお尋ねする質問です。 「お葬式の相談なのに、お骨のことを聞かれるなんて…」と驚かれる方も少なくありません。 しかし、お墓や供養の形が決まっているかどうかで、お葬式の内容や流れは大きく変わります。 供養環境を明確にすることが第一歩 「お墓がある」という方には、次のことを確認していただきます。 墓地の場所 墓地の形態(境内墓地、公営墓地、民営墓地、村墓地など) 管理費や連絡先 菩提寺がある場合は寺院名・宗派・連絡先・葬儀の作法 これらの情報を把握しておくことで、葬儀後の供養環境が明らかになります。 一方、「お墓がない」という方は、納骨先が決まっていないために悩まれるケースが多いです。岡山市内でも樹木葬や納骨堂など新しい選択肢が広がっていますが、どの方法を選ぶにしても、供養は残された家族にとって大切な場になります。だからこそ、元気なうちに家族で話し合っておくことが重要です。 お葬式を考えるときに大切なこと 実際に葬儀を考える際に確認しておきたいのは、次の5つです。 宗教の有無 葬儀の形式(家族葬・親族葬・一般葬など、参列範囲はどこまでか) 希望する場所(自宅・葬儀会館・寺院など) お骨の埋葬方法(墓地・納骨堂・樹木葬など) 本人や家族の意向 話しにくいからこそ、少しずつ お葬式の話題は切り出しにくいのが本音だと思います。ですが、例えば一緒にお墓参りをして、「このお墓はこういう経緯で建てられたんだよ」と話してみるのもきっかけになります。お墓がない場合でも、ご先祖様や家族の昔の話をする中で、自分たちの想いや希望を自然に伝えることができます。 勇気のいることかもしれませんが、「もっと話しておけばよかった…」と残された家族に後悔をさせないように、元気なうちに少しずつ語り合っていただければと思います。 次回は 「岡山葬儀事情⑤ ~葬儀の形式を考える~」 をお届けします。 岡山市で直葬・葬儀・家族葬なら『家族葬のファイング』へご相談下さい 岡山の直葬・葬儀・家族葬・一日葬なら家族葬のファイング【公式】[9.8万円~] 『家族葬のファイング』は、岡山の葬儀社として、多くのご家族をお手伝いしてきました。お一人おひとりの想いに寄り添い、故人様との最期の時間を大切にできる葬儀をご提案いたします。✅24時間365日お問合せ受付中✅費用を抑えた明瞭な家族葬プラン✅自宅へのお迎え、自宅葬対応✅福祉葬対応✅岡山北斎場 星空の郷での通夜、葬儀対応 専用ホームページ→家族葬のファイング/星空の郷お気軽にお問合せ下さいませ。 電話:0120-594-058 ≪記事≫川上 恵美子・終活カウンセラー1級・社会福祉士・おかやまスマイルライフ協会代表理事 【家族葬のファイング】 〒700-0044 岡山県岡山市北区三門西町3-17 《SNSはこちら》 画像をクリック! アンケート随時更新中! 《対応火葬場》地図はこちら⇩・岡山市東山斎場・岡山市岡山北斎場 星空の郷(倉敷市の火葬場も対応しています


岡山市で葬儀・家族葬をお考えの方へ 岡山の直葬・葬儀・家族葬・一日葬なら家族葬のファイング【公式】[9.8万円~] みなさん、こんにちは。岡山の葬儀社『家族葬のファイング』の石田信也(岡山市市民後見人)です。 当コラムでは葬儀社の観点から、成年後見人様にとって葬儀の際に役立つ内容を発信しております。 【令和8年1月1日(木)】 成年後見人が葬儀社と葬儀の打合せをする際に注意することは? 被後見人の方が亡くなられた際、葬儀の準備や打合せを行うのは成年後見人にとって大きな責任を伴う業務です。今回は、葬儀社との打合せで注意しておきたい点や、相続人がいる場合の話し合いの進め方など、実際の現場で役立つポイントをお伝えします。これから葬儀を担当される成年後見人の方にとって、少しでも参考になれば幸いです。 葬儀社との打合せでは、まず「誰が契約者になるのか」を明確にしておくことが重要です。成年後見人が葬儀を執り行う場合、契約者は後見人本人となり、登記事項証明書または審判書・確定証明書で資格を証明します。 次に、葬儀の内容や費用について相続人と事前に相談しておくことが大切です。被後見人の葬儀費用は、原則として被後見人の財産から支出しますが、相続人がいる場合は後の清算や費用負担に関して誤解が生じることがあります。そのため、 どのような形式で送るか(火葬式・家族葬・一般葬など) どの程度の費用をかけるか 費用の支払い方法(後払い・預かり金など)といった点を事前に説明し、同意を得ておくと安心です。 また、葬儀費用を被後見人の財産から支出する際には、家庭裁判所の許可が必要となる場合もあります。判断に迷うときは、あらかじめ裁判所に確認をとっておくことをおすすめします。 葬儀が終わったら、領収書や明細書を受け取り、後見事務報告書に添付できるように保管しておきましょう。 後見人が葬儀を行う場面は突然訪れることもあります。事前に流れと注意点を理解しておくことで、相続人や関係者との調整も円滑になり、被後見人の最期を丁寧にお見送りすることができます。 岡山市で直葬・葬儀・家族葬なら『家族葬のファイング』へご相談下さい 岡山の直葬・葬儀・家族葬・一日葬なら家族葬のファイング【公式】[9.8万円~] 『家族葬のファイング』は、岡山の葬儀社として、多くのご家族をお手伝いしてきました。お一人おひとりの想いに寄り添い、故人様との最期の時間を大切にできる葬儀をご提案いたします。✅24時間365日お問合せ受付中✅費用を抑えた明瞭な家族葬プラン✅自宅へのお迎え、自宅葬対応✅福祉葬対応✅岡山北斎場 星空の郷での通夜、葬儀対応 専用ホームページ→家族葬のファイング/星空の郷お気軽にお問合せ下さいませ。 電話:0120-594-058 ≪記事≫石田 信也・岡山市市民後見人・葬儀業界25年以上従事 【家族葬のファイング】 〒700-0044 岡山県岡山市北区三門西町3-17 《SNSはこちら》 画像をクリック! アンケート随時更新中! 《対応火葬場》地図はこちら⇩・岡山市東山斎場・岡山市岡山北斎場 星空の郷(倉敷市の火葬場も対応しています

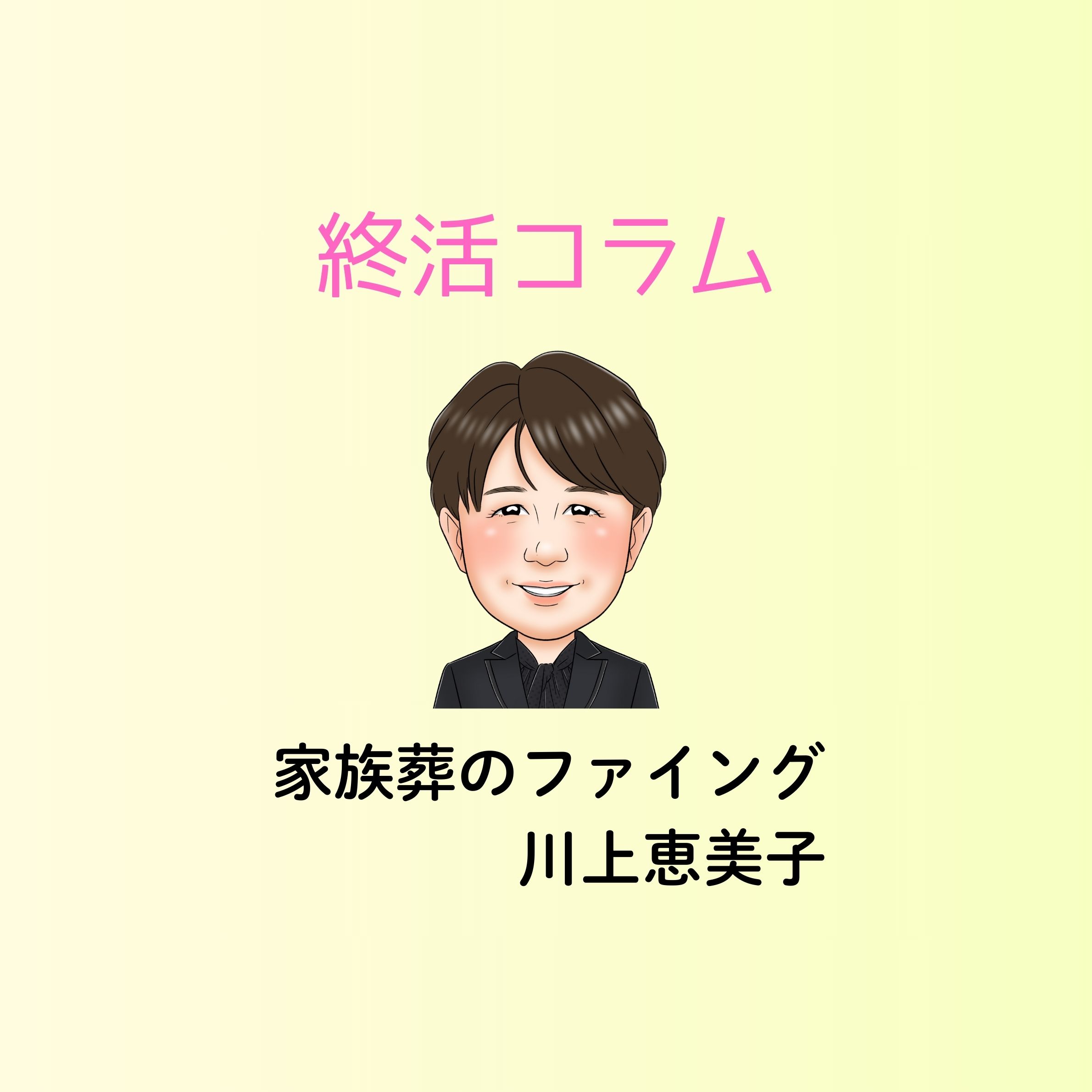
岡山市で葬儀・家族葬をお考えの方へ 岡山の直葬・葬儀・家族葬・一日葬なら家族葬のファイング【公式】[9.8万円~] 家族とはじめる終活終活カウンセラー 川上 恵美子 みなさん、こんにちは。岡山の葬儀社『家族葬のファイング』 川上恵美子です。 ~お葬式の在り方を考える~ 近年、岡山でもお葬式の簡素化が進んでいます。葬儀を行わず火葬のみを行う「直葬(ちょくそう/じきそう)」や、火葬後に遺骨を引き取らない「0葬(ぜろそう)」を選ぶ方が少しずつ増えてきました。 以前は「身寄りがない」という理由が多かったのですが、最近では 「家族に迷惑や負担をかけたくない」 「経済的な余裕がない」 「葬儀の必要性を感じない」 といった理由から選ばれるケースも見られます。 もちろん、昔のように義理や見栄で大規模なお葬式をする必要はありません。しかし、規模の大小にかかわらず「故人を感謝の気持ちで見送ること」は、どの時代でも大切な営みです。 私はこれまでのコラムで「葬儀は本人のためだけではなく、残された家族のためにも必要である」とお伝えしてきました。大切な人を亡くすことは心身に大きな負担を与えますが、その「死」をきっかけに命の尊さを知り、これからの生き方を見つめ直すこともできます。 葬儀の場は「大切なつながり」を生み出す貴重な機会です。 故人を知ってもらう 想いを語り合う 悲しみを分かち合う これらを通じて、残された家族が希望を持ち、周囲の人々に支えられながら生きていく力となります。悔いなく見送ることで、心穏やかに手を合わせ、ご先祖さまとのつながりも感じられるのです。 葬儀の在り方が変化している今だからこそ、「岡山での葬儀の選び方」「家族葬や直葬の特徴」「自分に合ったお葬式とは何か」を考えておくことが大切です。納得できる形で大切な人を見送るために、正しい知識と考え方を身につけておきましょう。 次回は 「岡山葬儀事情④ ~お葬式で必要な知識とは~」 をお伝えいたします。 次回は「岡山のお葬式事情③ ~知っておきたいお葬式の基本~」をお伝えします。 岡山市で直葬・葬儀・家族葬なら『家族葬のファイング』へご相談下さい 岡山の直葬・葬儀・家族葬・一日葬なら家族葬のファイング【公式】[9.8万円~] 『家族葬のファイング』は、岡山の葬儀社として、多くのご家族をお手伝いしてきました。お一人おひとりの想いに寄り添い、故人様との最期の時間を大切にできる葬儀をご提案いたします。✅24時間365日お問合せ受付中✅費用を抑えた明瞭な家族葬プラン✅自宅へのお迎え、自宅葬対応✅福祉葬対応✅岡山北斎場 星空の郷での通夜、葬儀対応 専用ホームページ→家族葬のファイング/星空の郷電話:0120-594-058までお気軽にお問合せ下さいませ。 【家族葬のファイング】 〒700-0044 岡山県岡山市北区三門西町3-17 ≪記事≫川上 恵美子・終活カウンセラー1級・社会福祉士・おかやまスマイルライフ協会代表理事 《SNSはこちら》 画像をクリック! アンケート随時更新中! 《対応火葬場》地図はこちら⇩・岡山市東山斎場・岡山市岡山北斎場 星空の郷(倉敷市の火葬場も対応しています


岡山市で直葬・葬儀・家族葬をお考えの方へ 岡山の直葬・葬儀・家族葬・一日葬なら家族葬のファイング最安値9.8万円~ みなさん、こんにちは。岡山の葬儀社『家族葬のファイング』です。 「大げさな葬儀はしたくないけれど、火葬場だけでお別れするのはあまりにも寂しい…」 岡山で直葬(火葬式)を検討されているご家族から、このようなご相談をよくいただきます。 一般的な「直葬」は、火葬場でのわずかな時間しかお別れができません。そこで家族葬のファイングがご提案しているのが、「出棺式プラン」です。直葬の手軽さと、お葬式の温かさを両立させた、新しいお見送りの形をご紹介します。 「出棺式」とは? 出棺式は、一言で言えば「お別れの儀式が付いた火葬式(直葬)」です。 通夜や告別式といった長時間の儀式は行いませんが、火葬場へ向かう前に、弊社の式場にて「お別れの時間」を設けています。お顔を見て、お花を添えて、ご家族のペースで最後のご挨拶ができるプランです。 「出棺式」プランの流れ 直葬98にはない「式場でのお別れ」が含まれるのが特徴です。 1.お迎え:病院や施設へお迎えに上がり、大切に搬送いたします。 2.弊社安置施設へご安置:火葬の日まで、専用の安置施設でお預かりします。 3.お打ち合わせ:火葬の日時や、式場でのお別れの進め方を相談します。 4.通夜…なし 5.葬儀…なし 6.葬儀場でのお別れ…あり【ここがポイント!】 火葬場へ行く前に、弊社の式場にてお集まりいただきます。 お棺の蓋を開け、お花を入れたり、お声をかけたり、最後の大切な時間を過ごせます。 7.出棺:式場から火葬場へ向けて出発します。 8.火葬場でのお別れ:火葬炉の前で、最後のご拝礼を行います。 9.火葬:火葬を執り行います。 10.収骨・散会:お骨上げを行い、現地にて解散となります。 なぜ「直葬」ではなく「出棺式」が選ばれるのか? 岡山にお住まいの方々が、あえてこのプランを選ばれる理由は3つあります。 ・「ちゃんとしてあげられた」という納得感: 火葬場のロビーで慌ただしくお別れするのとは違い、静かな式場で落ち着いて対面できるため、心の整理がつきやすくなります。 ・お花や思い出の品を入れられる: 直葬(火葬のみ)では難しい「お花入れ」ができるため、故人様を華やかに送り出すことができます。 ・低価格と満足度のバランス: 費用を14万円(税込15.4万円)〜に抑えつつ、家族葬に近い満足感を得られるため、現代のニーズに最もマッチしています。 こんな方におすすめです ・岡山市内で「安い直葬」を探しているが、少しは花を入れてあげたい。 ・家族だけでゆっくりお別れしたい。 ・儀式(お経など)は不要だが、最後に一目会ってから送り出したい。 まとめ:火葬式に「想い」をプラスする 「出棺式」は、形はシンプルですが、家族の想いをしっかりと形にできるプランです。「直葬で後悔したくない」とお考えなら、ぜひこのお別れ付きのプランをご検討ください。 ▶家族葬のファイング直葬98プラン▶家族葬のファイング出棺式14プラン▶家族葬のファイング出棺式17プラン 岡山市で直葬・葬儀・家族葬なら『家族葬のファイング』へご相談下さい 岡山の直葬・葬儀・家族葬・一日葬なら家族葬のファイング最安値 直葬9.8万円~ 『家族葬のファイング』は、岡山の葬儀社として、多くのご家族をお手伝いしてきました。お一人おひとりの想いに寄り添い、故人様との最期の時間を大切にできる葬儀をご提案いたします。✅24時間365日お問合せ受付中✅費用を抑えた明瞭な家族葬プラン✅自宅へのお迎え、自宅葬対応✅福祉葬対応✅岡山北斎場 星空の郷での通夜、葬儀対応 専用ホームページ→家族葬のファイング/星空の郷お気軽にお問合せ下さいませ。 電話:0120-594-058 【家族葬のファイング】 〒700-0044 岡山県岡山市北区三門西町3-17 《SNSはこちら》 画像をクリック! アンケート随時更新中! 《対応火葬場》地図はこちら⇩・岡山市東山斎場・岡山市岡山北斎場 星空の郷(倉敷市の火葬場も対応しています


岡山市で葬儀・家族葬をお考えの方へ 岡山の直葬・葬儀・家族葬・一日葬なら家族葬のファイング【公式】[9.8万円~] 【令和7年12月25日(木)】 みなさん、こんにちは。岡山の葬儀社『家族葬のファイング』の石田信也(岡山市市民後見人)です。 これまで、成年後見人の方が葬儀や火葬の申請を行う際に必要な書類などについてお伝えしてきましたが、今回は少し視点を変えて、「成年後見人が複数いる場合の役割分担」についてご紹介します。 成年後見人が2人で選任される場合、それぞれの担当が「財産管理」と「身上監護」に分かれることがあります。一見似ているようですが、実際には明確な役割の違いがあります。今回はその違いをわかりやすくまとめました。 【2人で成年後見を担当するケースとは】 家庭裁判所の判断により、1人の被後見人(ご本人)に対して2人の成年後見人が選任されることがあります。 これは、ご本人の生活や財産の状況が複雑な場合に、それぞれの分野に適した支援を行うために設けられる仕組みです。 【それぞれの役割】 成年後見人が2人いる場合、一般的には以下のように役割が分かれます。 ■ 財産管理を担当する成年後見人 預貯金・不動産・年金・医療費・施設利用料など、お金や契約に関することを管理します。葬儀費用の支払いも、この「財産管理」を担当する後見人が中心となって行います。 ■ 身上監護を担当する成年後見人 ご本人の生活や療養、施設入所、医療、介護など、日常生活に関わる判断やサポートを行います。葬儀に関しては、故人の希望や家族との調整など、「気持ちや生活面」に寄り添う役割を担うことが多いです。 【葬儀の場面では】 被後見人が亡くなられた場合、葬儀の手続きや火葬申請は「財産管理」を担当する成年後見人が行うのが基本です。 ただし、葬儀の内容(形式や場所など)については、「身上監護」を担当する後見人と相談のうえで決めるのが望ましいとされています。 つまり、 財産管理後見人 → 手続き・費用の責任者 身上監護後見人 → ご本人の思いや家族との調整役という形で、両者が協力しながら対応することが大切です。 【まとめ】 2人の成年後見人が選任されている場合、それぞれの立場でできること・できないことを理解しておくことで、葬儀やその後の手続きもスムーズに進めることができます。 今後も『家族葬のファイング』では、成年後見人の皆さまにとって実務の中で役立つ情報を分かりやすくお届けしてまいります。 岡山市で直葬・葬儀・家族葬なら『家族葬のファイング』へご相談下さい 岡山の直葬・葬儀・家族葬・一日葬なら家族葬のファイング【公式】[9.8万円~] 『家族葬のファイング』は、岡山の葬儀社として、多くのご家族をお手伝いしてきました。お一人おひとりの想いに寄り添い、故人様との最期の時間を大切にできる葬儀をご提案いたします。✅24時間365日お問合せ受付中✅費用を抑えた明瞭な家族葬プラン✅自宅へのお迎え、自宅葬対応✅福祉葬対応✅岡山北斎場 星空の郷での通夜、葬儀対応 専用ホームページ→家族葬のファイング/星空の郷お気軽にお問合せ下さいませ。 電話:0120-594-058 ≪記事≫石田 信也・岡山市市民後見人・葬儀業界25年以上従事 【家族葬のファイング】 〒700-0044 岡山県岡山市北区三門西町3-17 《SNSはこちら》 画像をクリック! アンケート随時更新中! 《対応火葬場》地図はこちら⇩・岡山市東山斎場・岡山市岡山北斎場 星空の郷(倉敷市の火葬場も対応しています


《お役立ち》岡山市の真宗大谷派の寺院をご紹介。 岡山の直葬・葬儀・家族葬一日葬なら家族葬のファイング【公式】[9.8万円~]岡山の葬儀社『家族葬のファイング』は真宗大谷派のご葬儀の対応実績有り。 【岡山市北区】 ●西寳寺(さいほうじ)所在地:岡山県岡山市北区表町3丁目5-40【地図】 電話:086-224-1600 【岡山市中区】 該当無し 【岡山市東区】 該当無し 【岡山市南区】 該当無し 岡山市で真宗大谷派の葬儀・家族葬なら『家族葬のファイング』へご相談下さい 岡山の直葬・葬儀・家族葬・一日葬なら家族葬のファイング【公式】[9.8万円~] 『家族葬のファイング』は、岡山市の葬儀社として、多くのご家族をお手伝いしてきました。お一人おひとりの想いに寄り添い、故人様との最期の時間を大切にできる葬儀をご提案いたします。✅24時間365日お問合せ受付中✅費用を抑えた明瞭な家族葬プラン✅自宅へのお迎え、自宅葬対応✅福祉葬対応✅岡山北斎場 星空の郷での 通夜、葬儀対応→家族葬のファイング/星空の郷お気軽にお問合せ下さいませ。 電話:0120-594-058 【家族葬のファイング】 〒700-0044 岡山県岡山市北区三門西町3-17 《SNSはこちら》 画像をクリック! アンケート随時更新中! 《対応火葬場》地図はこちら⇩・岡山市東山斎場・岡山市岡山北斎場 星空の郷(倉敷市の火葬場も対応しています


岡山市で直葬・葬儀・家族葬をお考えの方へ 岡山の直葬・葬儀・家族葬・一日葬なら家族葬のファイング最安値9.8万円~ みなさん、こんにちは。岡山の葬儀社『家族葬のファイング』です。 岡山で「お葬式は身内だけでシンプルに済ませたい」「儀式を行わず、火葬のみ(直葬)で送りたい」というご要望が増えています。 しかし、いざ探してみると「直葬と火葬式の違いは?」「どこまで料金に含まれているの?」と不安に思う方も少なくありません。 そこで、家族葬のファイングで最もシンプルなプラン「直葬98」について、その内容と流れを分かりやすく解説します。 直葬98プランとは? 「直葬98プラン」は、通夜・告別式といった儀式を一切行わず、火葬のみを行う最もシンプルな葬送スタイルです。 一般的に「直葬(ちょくそう)」や「火葬式」と呼ばれるものの中でも、特に費用を抑えたい方に選ばれています。 「葬儀にお金はかけられないけれど、失礼のないよう最低限のことはしてあげたい」というご家族に最適なプランです。 「直葬98」プランの流れ お申し込みから散会まで、無駄のない10のステップで進みます。 お迎え:病院や施設など、ご指定の場所まで専用車でお迎えに上がります。 弊社安置施設へご安置:諸事情によりご自宅へ連れて帰れない場合もご安心ください。弊社の安置施設にてお預かりします。 お打ち合わせ:火葬の日時やお手続きについて、スタッフと詳細を決定します。 通夜…なし 葬儀…なし 葬儀場でのお別れ…なし 火葬場での待ち合わせ・お別れ:当日、火葬場のロビー等で集合。火葬炉の前で最後のお別れ(合掌など)を行います。 火葬:火葬が執り行われます。 収骨:ご遺族の手でお骨を拾っていただきます。 散会:現地にて解散となります。 このプランが「岡山」で選ばれる理由 岡山市内での葬儀相場に比べ、9.8万円(税込10.78万円)〜という価格設定は非常にコンパクトです。 ・無駄を省いた明快な料金:儀式をしない分、費用を最小限に抑えられます。・手間がかからない:準備や参列者への対応がほぼ不要なため、精神的・体力的な負担が軽減されます。・ファイングの安心感:安価であっても、ご遺体の搬送や役所手続きの代行など、プロのスタッフが最後までサポートいたします。 注意点:後悔しないために 直葬98は「式場での対面・お別れ」が含まれていません。 もし「最後にお花をたくさん入れてあげたい」「少しの時間でも式場で顔を見てお別れしたい」という場合は、弊社の「出棺式14」以上のプランがおすすめです。 まとめ:岡山で最もシンプルな「直葬」なら 家族葬のファイングの「直葬98」は、現代のニーズに合わせた究極のシンプルプランです。 「形式にはこだわらないが、しっかりと火葬だけはしてあげたい」とお考えの方は、ぜひ一度ご相談ください。24時間365日お迎えに上がります。 ▶家族葬のファイング直葬98プラン▶家族葬のファイング出棺式14プラン▶家族葬のファイング出棺式17プラン 岡山市で直葬・葬儀・家族葬なら『家族葬のファイング』へご相談下さい 岡山の直葬・葬儀・家族葬・一日葬なら家族葬のファイング最安値 直葬9.8万円~ 『家族葬のファイング』は、岡山の葬儀社として、多くのご家族をお手伝いしてきました。お一人おひとりの想いに寄り添い、故人様との最期の時間を大切にできる葬儀をご提案いたします。✅24時間365日お問合せ受付中✅費用を抑えた明瞭な家族葬プラン✅自宅へのお迎え、自宅葬対応✅福祉葬対応✅岡山北斎場 星空の郷での通夜、葬儀対応 専用ホームページ→家族葬のファイング/星空の郷お気軽にお問合せ下さいませ。 電話:0120-594-058 【家族葬のファイング】 〒700-0044 岡山県岡山市北区三門西町3-17 《SNSはこちら》 画像をクリック! アンケート随時更新中! 《対応火葬場》地図はこちら⇩・岡山市東山斎場・岡山市岡山北斎場 星空の郷(倉敷市の火葬場も対応しています

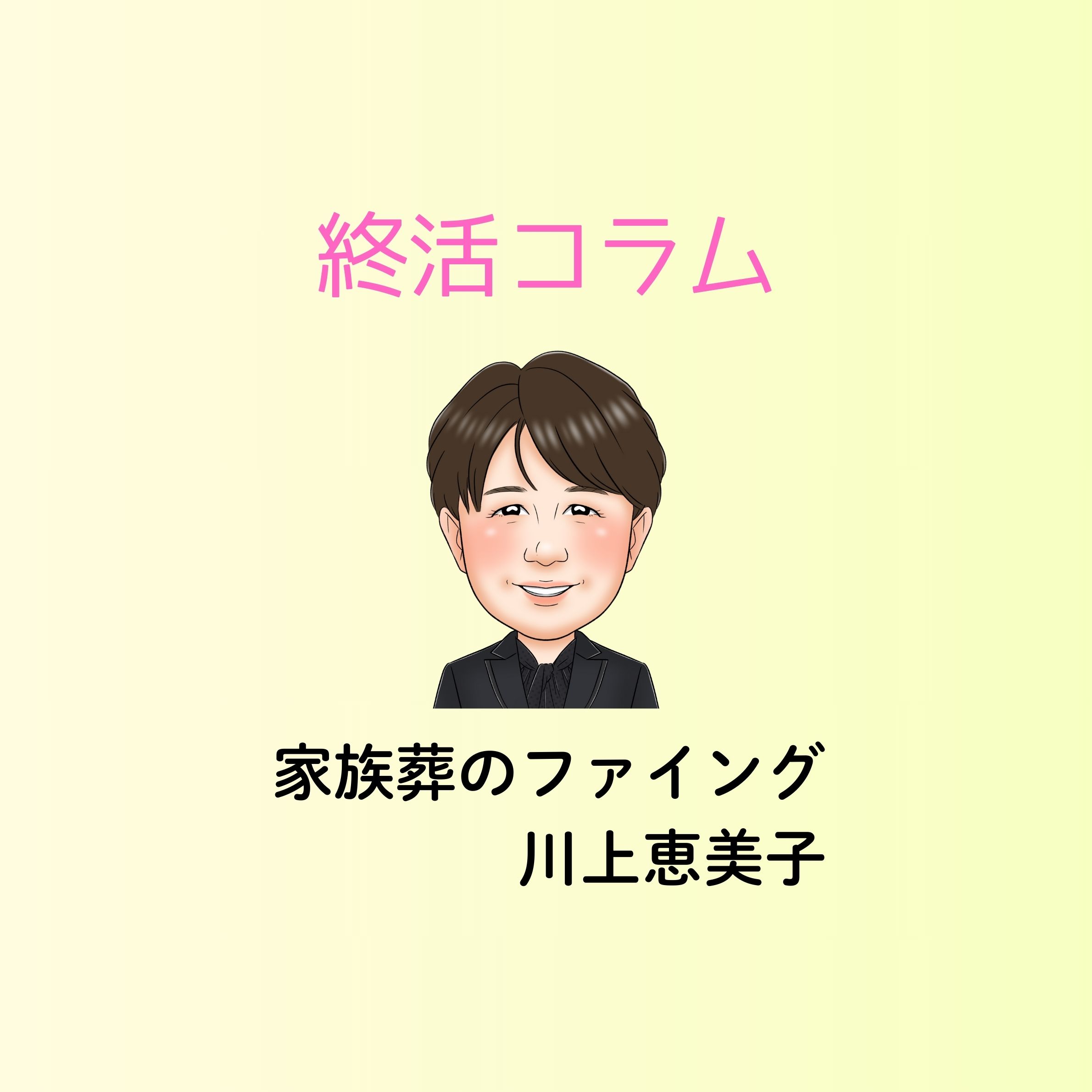
岡山市で葬儀・家族葬をお考えの方へ 岡山の直葬・葬儀・家族葬・一日葬なら家族葬のファイング【公式】[9.8万円~] 家族とはじめる終活終活カウンセラー 川上 恵美子 みなさん、こんにちは。岡山の葬儀社『家族葬のファイング』 川上恵美子です。 皆さんは、ご自身のお葬式について考えたことはありますか。「そんなことを考えるなんて縁起でもない」と思う方も多いでしょう。けれども、大切なご家族のことを想うと、「自分が亡くなったあと、残された家族は大丈夫だろうか」と心配になる方は少なくありません。 ~自分のお葬式を考える~ お葬式は「義務」ではない 実際にご相談を受ける中で、「お葬式は本当に必要でしょうか?」という質問をされることがあります。法律で定められているのは、死亡届の提出と火葬または埋葬といった手続きであり、「お葬式」を行うこと自体は義務ではありません。 しかし私は、お葬式は亡くなられた方のためというより、残された大切な家族のために必要な時間だと考えています。 お葬式は家族の「心の支え」 人は一人では生きていけません。大切な人の死を受け入れ、向き合い、折り合いをつけて前を向くためには、家族や友人、地域社会からの支えが必要です。そして、その最初の時間と場を与えてくれるのが「お葬式」なのです。 岡山でも近年は「家族葬」や「一日葬」「直葬」など、形式が多様化しています。けれどもどの形であっても、**お葬式は「悲しみを分かち合う時間」であり、「残された人の心を支える儀式」**であることに変わりはありません。 後悔のないお別れのために もしもの時は突然訪れます。大切な人を失った悲しみの中、残された家族は心身ともに大きな負担を抱えることになります。しかし現実には、悲しみに浸る暇もなく、葬儀の準備を淡々と進めなければなりません。冷静な判断力を保てる人は少なく、多くの方がお葬式を「葬儀社に言われるまま、あっという間に終えてしまった」と振り返ります。 その結果、 「これで本当に良かったのだろうか」 「もっとこうしてあげたかった」といった後悔の声を聞くことが少なくありません。 こうした思いを家族に残さないためには、元気なうちから自分のお葬式について話し合っておくことがとても大切です。 家族で話し合っておくことの大切さ 「お葬式をどうしたいのか」「どのように送りたいのか」といった希望を、前もって共有しておけば、残されたご家族は迷うことなく判断できます。そしてその準備が、ご家族にとっては「後悔を減らし、安心して送り出せた」という心の支えになるのです。 岡山市でも「家族葬」のご相談が増えており、事前にご自身の希望を伝える方が確実に増えてきています。これは、「大切な家族に負担をかけたくない」という優しさの表れでもあります。 まとめ お葬式は法律上の義務ではないが、家族にとって大切な心の支えになる。 形式は多様化しているが、どの葬儀にも「悲しみを分かち合う時間」という意味がある。 家族で事前に話し合っておくことで、残された人の後悔を少なくできる。 次回は「岡山のお葬式事情③ ~知っておきたいお葬式の基本~」をお伝えします。 岡山市で直葬・葬儀・家族葬なら『家族葬のファイング』へご相談下さい 岡山の直葬・葬儀・家族葬・一日葬なら家族葬のファイング【公式】[9.8万円~] 『家族葬のファイング』は、岡山の葬儀社として、多くのご家族をお手伝いしてきました。お一人おひとりの想いに寄り添い、故人様との最期の時間を大切にできる葬儀をご提案いたします。✅24時間365日お問合せ受付中✅費用を抑えた明瞭な家族葬プラン✅自宅へのお迎え、自宅葬対応✅福祉葬対応✅岡山北斎場 星空の郷での通夜、葬儀対応 専用ホームページ→家族葬のファイング/星空の郷お気軽にお問合せ下さいませ。 電話:0120-594-058 ≪記事≫川上 恵美子・終活カウンセラー1級・社会福祉士・おかやまスマイルライフ協会代表理事 【家族葬のファイング】 〒700-0044 岡山県岡山市北区三門西町3-17 《SNSはこちら》 画像をクリック! アンケート随時更新中! 《対応火葬場》地図はこちら⇩・岡山市東山斎場・岡山市岡山北斎場 星空の郷(倉敷市の火葬場も対応しています


岡山市で葬儀・家族葬をお考えの方へ 岡山の直葬・葬儀・家族葬・一日葬なら家族葬のファイング【公式】[9.8万円~] 【令和7年12月18日(木)】 みなさん、こんにちは。岡山の葬儀社『家族葬のファイング』石田信也(岡山市市市民後見人)です。 これまで、個人の成年後見人が葬儀を行う際の手続きについてお伝えしてきましたが、今回は法人が成年後見人として被後見人(ご本人)の葬儀や死亡届を行う場合に必要な書類についてご紹介します。 岡山市でも法人が後見を担うケースが増えており、必要書類や届出人の記載方法など、個人後見人とは異なる点があります。 成年後見人が法人(社会福祉法人・一般社団法人・NPO法人など)である場合、被後見人の死亡届や火葬の申請を行う際には、次の2種類の書類が必要です。 【必要な書類】 登記事項証明書 成年後見登記の内容を証明するもので、法人が成年後見人であることを確認するために提出します。 履歴事項全部証明書(法人登記簿謄本) 法人の代表者や所在地など、法人の登記内容を証明する書類です。 登記事項証明書だけでは代表者が誰か確認できないため、この証明書の添付が求められます。 【死亡届の届出人の署名について】 被後見人の死亡届を提出する際、届出人欄には法人名ではなく、法人代表者の氏名を記入します。 たとえば、 届出人 ○○法人 代表者 山田太郎 のように、法人名と代表者名を併記する形になります。 岡山市ではこの形式で届出が受理されます。 【まとめ】 法人が成年後見人として葬儀や火葬の申請を行う場合、必要な書類は「登記事項証明書」と「履歴事項全部証明書」の2点です。また、死亡届の届出人は「法人名+代表者氏名」で記載することが必要です。 法人後見では、手続きが個人後見よりも少し複雑になりますが、事前に準備しておくことでスムーズに葬儀手続きが進められます。 今後も『家族葬のファイング』では、成年後見人の皆さまに役立つ実務情報を発信してまいります。 岡山市で直葬・葬儀・家族葬なら『家族葬のファイング』へご相談下さい 岡山の直葬・葬儀・家族葬・一日葬なら家族葬のファイング【公式】[9.8万円~] 『家族葬のファイング』は、岡山の葬儀社として、多くのご家族をお手伝いしてきました。お一人おひとりの想いに寄り添い、故人様との最期の時間を大切にできる葬儀をご提案いたします。✅24時間365日お問合せ受付中✅費用を抑えた明瞭な家族葬プラン✅自宅へのお迎え、自宅葬対応✅福祉葬対応✅岡山北斎場 星空の郷での通夜、葬儀対応 専用ホームページ→家族葬のファイング/星空の郷お気軽にお問合せ下さいませ。 電話:0120-594-058 ≪記事≫石田 信也・岡山市市民後見人・葬儀業界25年以上従事 【家族葬のファイング】 〒700-0044 岡山県岡山市北区三門西町3-17 《SNSはこちら》 画像をクリック! アンケート随時更新中! 《対応火葬場》地図はこちら⇩・岡山市東山斎場・岡山市岡山北斎場 星空の郷(倉敷市の火葬場も対応しています

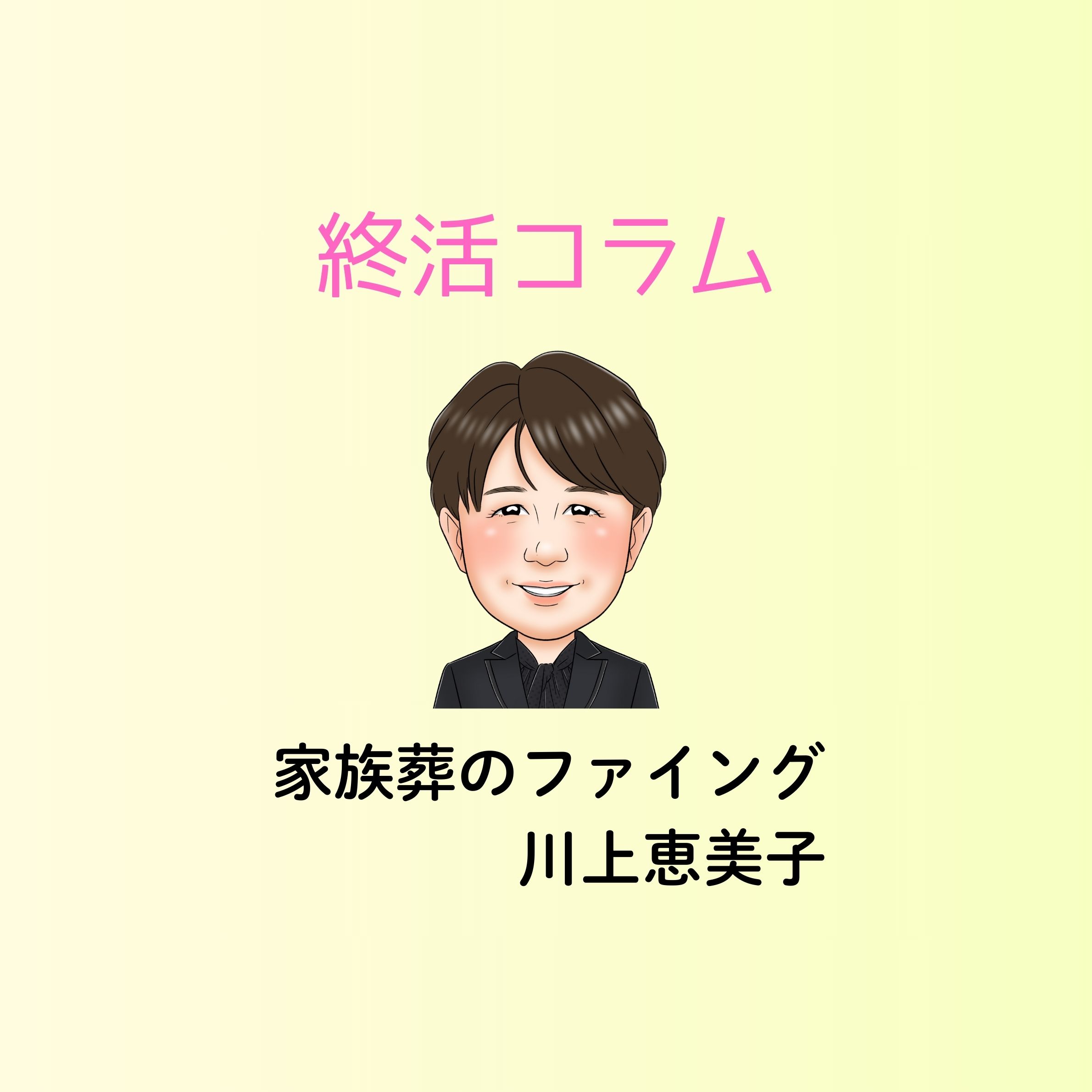
岡山市で葬儀・家族葬をお考えの方へ 岡山の直葬・葬儀・家族葬・一日葬なら家族葬のファイング【公式】[9.8万円~] 家族とはじめる終活終活カウンセラー 川上 恵美子 みなさん、こんにちは。岡山の葬儀社『家族葬のファイング』 川上恵美子です。 今回は「岡山のお葬式事情」をテーマに、私自身の体験を交えながらお伝えします。 ~新しい人生の始まり~ 「死」と向き合うことに戸惑った日々 結婚を機に、岡山市で家業である葬儀社に入社した当初、私は大きな戸惑いの中にいました。 以前は旅行会社の添乗員をしていた私にとって、人の「死」と向き合う現場は、あまりにも未知の世界だったからです。 多くの方にとって、お葬式は「できれば避けたいもの」であり、進んで準備をしたいことではありません。しかし、岡山の地で数多くのご葬儀をお手伝いする中で、私は一つの大切な真実に気づかされました。お葬式は単なる別れの儀式ではなく、残されたご家族が新しい一歩を踏み出すための、かけがえのない時間だということです。 忘れられない奥様の言葉 そんなある日、80代の奥様から「川上さん、本当にありがとう。これからもよろしくね」と声をかけられました。まだ葬儀の知識も経験も浅かった私に、何度も手を握って感謝してくださったのです。 そのとき私にできたことは、奥様からご主人との思い出話を聴くことだけでした。「川上さん、主人の顔を見てくれる?とてもいい顔をしているでしょう。話を聞いてくれて本当にありがとう」――ご主人様を見つめる奥様の笑顔は、今でも忘れられません。 後悔しない葬儀のために知っておきたい「岡山の葬儀事情」 葬儀が終わった後、奥様から「私のときは子どもたちに迷惑をかけたくない。何か準備をした方がいいかしら」と相談を受けました。 特にお急ぎの場合は、落ち着いて判断する余裕がなくなってしまうものです。 私は「家族会議」というほど大げさではなく、家族みんなで集まり、ご主人の葬儀についての感想や意見を話し合う場を提案しました。大げさなものではなく、葬儀を通じて感じたこと、良かった点や「もっとこうしてあげたかった」という本音を語り合う場です。そこでは「反省」や「後悔」といった普段は言いづらいことも出ましたが、不思議と皆さんは笑顔で話していたのです。 実は、この「振り返り」こそが、次に備えるための最も有益な情報になります。岡山でも「家族に迷惑をかけたくない」と直葬を希望される方は多いですが、いざその時になってご親戚から「なぜ式をしないのか」と問われ、困惑するケースも少なくありません。事前の相談や家族間での意思疎通があるだけで、葬儀の不安は驚くほど解消されます。 「自分らしいお葬式」は愛情表現の一つ 私は「終活」や「葬儀」とは、単なる死後の準備ではなく、自分と大切な家族への愛情表現だと考えています。だからこそ、家族の思いや考えをじっくり聴き、その橋渡しをすることが私の使命だと思うようになりました。 終活や事前相談は、決して縁起の悪いことではありません。むしろ、自分と大切な家族を守るための「究極の愛情表現」です。岡山で家族葬や直葬を検討されているなら、まずは「どんな風に送りたいか、送られたいか」という小さな希望を言葉にすることから始めてみてください。 私たちは、岡山の皆様が抱える葬儀への不安に寄り添い、透明性の高い情報提供を通じて、納得のいくお別れの形をサポートし続けます。 まとめ 岡山市内でも「家族葬」や「直葬」といった、形式にとらわれない新しいお葬式の形が主流になりつつあります。お葬式は亡くなった方を送る儀式であると同時に、残されたご家族がこれからの人生を前向きに歩むための大切な節目です。 もし、岡山でのお葬式の流れや費用、直葬の具体的な進め方について疑問があれば、いつでも私たちにご相談ください。元気なうちから少しずつ情報を集め、家族で話し合っておくことが、後悔のないお葬式への一番の近道となります。 次回は「岡山のお葬式事情②」をお届けします。 岡山市で直葬・葬儀・家族葬なら『家族葬のファイング』へご相談下さい 岡山の直葬・葬儀・家族葬・一日葬なら家族葬のファイング【公式】[9.8万円~] 『家族葬のファイング』は、岡山の葬儀社として、多くのご家族をお手伝いしてきました。お一人おひとりの想いに寄り添い、故人様との最期の時間を大切にできる葬儀をご提案いたします。✅24時間365日お問合せ受付中✅費用を抑えた明瞭な家族葬プラン✅自宅へのお迎え、自宅葬対応✅福祉葬対応✅岡山北斎場 星空の郷での通夜、葬儀対応 専用ホームページ→家族葬のファイング/星空の郷お気軽にお問合せ下さいませ。 電話:0120-594-058 ≪記事≫川上 恵美子・終活カウンセラー1級・社会福祉士・おかやまスマイルライフ協会代表理事 【家族葬のファイング】 〒700-0044 岡山県岡山市北区三門西町3-17 《SNSはこちら》 画像をクリック! アンケート随時更新中! 《対応火葬場》地図はこちら⇩・岡山市東山斎場・岡山市岡山北斎場 星空の郷(倉敷市の火葬場も対応しています


《お役立ち》岡山市北区の浄土真宗本願寺派の寺院をご紹介。 岡山の直葬・葬儀・家族葬・一日葬なら家族葬のファイング【公式】[9.8万円~] 【岡山市北区】 ●光善寺(こうぜんじ)【ホームページ】所在地:岡山県岡山市北区下伊福1丁目6-19【地図】 電話:086-252-6404 ●浄覚寺(じょうかくじ)【ホームページ】所在地:岡山県岡山市北区番町2丁目7-20【地図】 電話:086-222-3475 ●光清寺(こうせいじ)【ホームページ】所在地:岡山県岡山市北区清輝橋1丁目4-8【地図】 電話:086-223-3081 ●光明寺(こうみょうじ)【ホームページ】所在地:岡山県岡山市北区庭瀬767【地図】 電話:086-293-1053 ●正善寺岡山分院(しょうぜんじおかやまぶんいん)【ホームページ】所在地:岡山県岡山市北区中仙道2丁目1-31【地図】 電話:086-241-3681 【岡山市 寺院一覧】浄土真宗本願寺派(北区) 【岡山市 寺院一覧】浄土真宗本願寺派(中区) 【岡山市 寺院一覧】浄土真宗本願寺派(東区) 【岡山市 寺院一覧】浄土真宗本願寺派(南区) 岡山で直葬・葬儀・家族葬なら『家族葬のファイング』へご相談下さい(浄土真宗本願寺派の葬儀対応) 岡山の直葬・葬儀・家族葬・一日葬なら家族葬のファイング【公式】[9.8万円~] 『家族葬のファイング』は、岡山市の葬儀社として、多くのご家族をお手伝いしてきました。お一人おひとりの想いに寄り添い、故人様との最期の時間を大切にできる葬儀をご提案いたします。✅24時間365日お問合せ受付中✅費用を抑えた明瞭な家族葬プラン✅自宅へのお迎え、自宅葬対応✅福祉葬対応✅岡山北斎場 星空の郷での通夜、葬儀対応 専用ホームページ→家族葬のファイング/星空の郷お気軽にお問合せ下さいませ。 電話:0120-594-058 【家族葬のファイング】 〒700-0044 岡山県岡山市北区三門西町3-17 《SNSはこちら》 画像をクリック! アンケート随時更新中! 《対応火葬場》地図はこちら⇩・岡山市東山斎場・岡山市岡山北斎場 星空の郷(倉敷市の火葬場も対応しています)


《お役立ち》岡山市中区の浄土真宗本願寺派の寺院をご紹介。 岡山の直葬・葬儀・家族葬・一日葬なら家族葬のファイング【公式】[9.8万円~] 【岡山市中区】 ●真宗寺(しんしゅうじ)【ホームページ】所在地:岡山県岡山市中区江並132-3【地図】 電話:086-276-8386 ●浄教寺(じょうきょうじ)所在地:岡山県岡山市中区御成町10-26【地図】 電話:086-272-3468 ●源照寺(げんしょうじ)所在地:岡山県岡山市中区新京橋1丁目3-21【地図】 電話:086-272-1478 【岡山市 寺院一覧】浄土真宗本願寺派(北区) 【岡山市 寺院一覧】浄土真宗本願寺派(中区) 【岡山市 寺院一覧】浄土真宗本願寺派(東区) 【岡山市 寺院一覧】浄土真宗本願寺派(南区) 岡山で直葬・葬儀・家族葬なら『家族葬のファイング』へご相談下さい(浄土真宗本願寺派の葬儀対応) 岡山の直葬・葬儀・家族葬・一日葬なら家族葬のファイング【公式】[9.8万円~] 『家族葬のファイング』は、岡山市の葬儀社として、多くのご家族をお手伝いしてきました。お一人おひとりの想いに寄り添い、故人様との最期の時間を大切にできる葬儀をご提案いたします。✅24時間365日お問合せ受付中✅費用を抑えた明瞭な家族葬プラン✅自宅へのお迎え、自宅葬対応✅福祉葬対応✅岡山北斎場 星空の郷での通夜、葬儀対応 専用ホームページ→家族葬のファイング/星空の郷お気軽にお問合せ下さいませ。 電話:0120-594-058 【家族葬のファイング】 〒700-0044 岡山県岡山市北区三門西町3-17 《SNSはこちら》 画像をクリック! アンケート随時更新中! 《対応火葬場》地図はこちら⇩・岡山市東山斎場・岡山市岡山北斎場 星空の郷(倉敷市の火葬場も対応しています)
